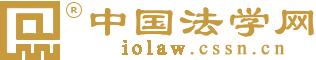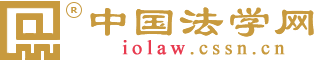王恵茹:サプライチェーン人権責任の境界比較分析と法理的反省
内容要旨:グローバルなサプライチェーンの冗長性と複雑さが増すにつれて、サプライチェーンの人権に関する責任は多国籍企業の問責分野で論争の焦点となった。近年、人権の責務を果たす分野の立法実践は、自発的な軟法から強制的な硬法へ転換し、会社の自身の業務に対する責務からサプライチェーン全体の責務を果たすように拡大する傾向を示している。しかし、人権の責務をどの程度サプライチェーンに広げ、どのようなモデルで国内の法律政策に組み入れるべきかについて各国の実践的立場は大きく異なる。サプライチェーンの人権の責務を果たす境界をめぐる国際ソフト法の多中心化解釈は、解釈の多元化、限界のモデル化、手続き化を実施するリスクに直面するだけでなく、誤読と乱用されるリスクにも直面している。同時に、一部の国と地域は強制的なサプライチェーンの人権責任を果たす立法を極力推進し、世界のサプライチェーンの安定と国際経済貿易秩序に深い影響を与えている。このバタンで、サプライチェーンの人権が責任を果たす合理的な境界を検討することは重要な意義がある。サプライチェーン人権の責務は一概に論じるべきではなく、法的要素の合理性と現実的要素の複雑性を考慮し、会社とサプライチェーンにおけるマイナス人権影響間の異なるつながりの程度と状況に応じて適用すべきである。中国は特に強制的なサプライチェーン人権の責務を果たす立法の「寒セミ効果」を警戒し、国家サプライチェーンの安全と国際サプライチェーン競争を高度に重視し、国連の枠組みの下でのボランティア人権の責務を果たす実施を積極的に推進し、中国が商工業と人権分野の国際ルール制定に参与する発言権の向上を加速させなければならない。
キーワード:商工業と人権、人権責任果たし、サプライチェーン、国際ソフト法、強制的な責任果たし
著者:王恵茹、中国社会科学院国際法研究所ア研究シスタント
出典:『人権』2024年第2期。