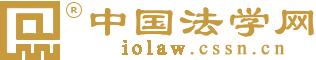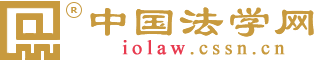習近平総書記は、中央全面法による国家統治委員会の第1回会議で、全面法治国はシステム工学であり、統一的に配慮し、重点を把握し、全体的な計画を把握し、システム性、全体性、協同性をさらに重視しなければならないと指摘した。これはシステム論的思考の法学分野における重要な体現であり、法学の各サブシステムの内部発展及び外部環境との構造結合の促進に指導的意義がある。
著名な刑法学者である储槐植教授の「刑事一体化」にヒントを得て、筆者は立体刑法学の思想を提唱した。立体刑法学は、刑法を平面ではなく、立体的で動的で一元的ではなく、多元的な理念と方法で研究することが刑法正義の実現にさらに役立つと主張している。刑事一体化であれ立体刑法学であれ、すべて体系的思考の産物であり、それらはすべて一つのキーワードを持っている:储槐植教授は刑法生存関係を提示し、社会経済と刑法、その他の省庁法と刑法など15つの関連性を挙げた。刑法と関連分野の関係を専門的に研究する独立刑法分科である「関係刑法学」を作らなければならないという主張だ。
例えば、刑法教義学と社会科学刑法学は、一連の刑法学研究において重要な関係である。刑法教義学は刑法学というサブシステムが存在する基盤であるが、刑法の運用は孤立したものではなく、社会という大きなシステムに環境刺激を受けて反応することにより、刑法への社会学、経済学、政治学、心理学、電波学などの社会科学の応用が必要かつ実行可能であることを決定した。刑法教義学のない社会科刑法学は空虚だが、社会科刑法学のない刑法教義学も狭いと言える。
刑法と刑事政策の関係については、刑法と刑事政策の分離を強調し、融合を強調するリスト•ディバイドとロクシン貫通説がある。現代社会では累犯重懲戒、自白軽懲戒、赦免など刑事政策の内容が刑に処せられる刑法の刑事政策化傾向を見せている一方、法治国家は刑法規定の範囲内で刑事政策を樹立しなければならないと要求している。このような点で、貫通説が今の時代にふさわしいが、刑法と刑事政策をどのようによりよく貫通して融合させるか、具体的な問題点はさらに深く研究しなければならない。
犯罪者と被害者の関係も重要な関係だ。犯罪の葛藤は犯罪者と被害者から始まったもので、国家検察官制度は被害者の正義を助けるために作られたが、実践被害者の欲求は十分に満たされなかった。このような状況で、国際的に'回復的司法'が復活し、中国の司法伝統の仲裁制度が現地資源として認識されている。近年、我が国における刑事和解はこの方面の証拠と見なすことができる。回復的司法に触発され、刑法の法的結果は伝統的な刑罰と保安処分二元制から刑罰、保安処分と賠償など非刑罰措置の三元制へと広がっている。
刑法学界の学派争いは学術的繁栄と深化学術的見解を促進するのに役立つに違いない。学閥争いは特定の歴史的段階の産物であることを自覚しなければならない。歴史的に学派争いは特定の社会的背景と結びついているが、特に経世済用刑法制度と刑法学は結局、折衷に向かっており、行為刑法と行為者刑法の争いもそうであり、報応刑と予防刑の争いもそうであり、形式解釈と実質解釈、行為無価値と結果無価値、主観主義と客観主義などがそうだ。
刑法研究はマクロとミクロの関係をうまく処理しなければならない。私たちは一つ一つのミクロ問題において具体的に深く研究して、「大げさ」に川河を形成するだけでなく、マクロ的に刑法学研究の理念、方法と方向を把握して、中国刑法学研究の全体像を作り出す必要がある。
これと関連して、私たちは真実と虚構の関係をうまく処理しなければならない。刑法学研究は法規範の適用に基づいた技術的作業だが、価値判断とも密接な関連がある。最近になって、技術的な面で相対的に強調が多く、機械的な法執行が相次ぎ、一部影響力のある事件の1審裁判は法的根拠はあるものの、社会的論議を呼んでいる。最高人民裁判所が「天理、国法、人情の統一」を要求したのは、新時代を背景に公正正義に対する要求が高まったためだ。現実と虚構、明確性と曖昧性、技術と理念の関係を現代立法と司法解釈が適切に処理することを要求したのだ。
マルクス主義の古典作家たちはすでに人間が社会関係の産物だと指摘している。関係が非常に複雑で、関係がどこにでもある。刑法は社会関係を扱う正義の学問として体系的思考を備えてこそ、複雑な関係迷妄の中で自分をもっとよく認識して正義を求めることができる。
著者:劉仁文、中国社会科学院法学研究所刑法研究室主任、研究員、中国社会科学院大学法学部教授、博士課程の指導教授。
出所:「民主と法治」2023年第29号。