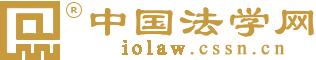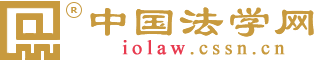著者:孫憲忠
「中華人民共和国行政再議法」は我が国の法律体系における地位が非常に重要であり、それは法に基づいた行政原則を貫徹し、ひいては法治原則を実行するために最も重要な法律制度の一つである。同法は第9期全国人民代表大会常務委員会が1999年4月29日に可決し、1999年10月1日から施行された。同法は2009年、2017年の2回の改正を経た。2023年6月26日、「中華人民共和国行政再議法(改正草案)」(以下改正草案と略称する)は第14期全国人民代表大会常務委員会第3回会議の審議を要請した。改正草案の審議稿に対して、私は次の9つの方面の建議を提出して参考に供する。[1]
一、行政再議請求権者主体の規定を整備する
改正草案第2条第1項は、「公民、法人又はその他の組織は、行政機関の行政行為がその合法的権益を侵害していると考え、行政再議機関に行政再議申請を提出し、行政再議機関は行政再議事件を処理し、本法を使用する」と規定している。この条文及び改正草案全体において、行政再議主体は依然として「公民、法人又はその他の組織」の概念を使用しており、我が国の民法典で使用されている「自然人、法人、非法人組織」という法律関係主体の概念は採用されていない。草案を改訂するこのやり方は適切ではなく、すべて「民法典」の規定に従って修正することを提案したい。
法律関係理論の主体の概念は、単なる法律上の呼称問題ではなく、法律の人への適用範囲に関する大きな問題、つまり誰がこの法を適用できるか、誰が適用できないかという問題である。だから、主体の規定については、法律の制定において最初に明確にすべき問題である。行政再議法は1999年に制定された時、「公民、法人、またはその他の組織」という概念を採用していたが、当時の状況から見ると、この概念の使用は正確ではなく、今から見ると、この概念の使用はもっと正確ではない。改革開放以来、我が国国内には中華人民共和国の公民としての身分を持たない多くの自然人(外国人と無国籍人)が暮らしており、他にも外国企業の事務所連絡所などの非法人組織体があるからだ。彼らは我が国内に住んで生活しており、もちろん我が国の行政管理を受けなければならないので、当然行政再議に関わる法律問題が発生する。もちろん、彼らも行政再議を提起する権利を持っている。そのため、行政再議法は「民法典」の主体に関する規定を受け入れ、「自然人、法人、非法人組織」の概念を行政再議申請者の概念としなければならない。
公民という概念は、我が国の憲法に基づいても公認された法理に基づいても、特定の国の国籍を持つ自然人である。我が国の「憲法」第33条第1項の規定によると、「中華人民共和国国籍を有する者はすべて中華人民共和国公民である」ことから、外国人は我が国公民の中には含まれていないことがわかる。したがって、我が国に居住して生活している外国人に対して、彼らを行政再議の申請者主体として規定しないと、人々はこの規定を外国人が我が国の行政管理の管轄を受けていないと理解したり、この法律を外国人の行政管理に適用されていないと理解したりすることが深刻な結果になる。しかし、現実はそうではなく、我が国の立法の本意もそうではない。だから、この概念は修正しなければならない。
私は「公民」という概念の代わりに「自然人」という概念を使うことを提案し、あるいはこれまでのいくつかの立法のやり方に従って、「公民」の後ろに括弧をつけて「自然人」と書くことができ、あるいは「非中華人民共和国公民が行政再議を提起した場合、本法を適用する」と法律の付則に補足することができる。
「他の組織」という概念については、民法典編纂時に明確な議論がなされていたが[2]、最終的には「非法人組織」という概念が用いられた。「他の組織」に比べて、「非法人組織」という概念は法律表現上より正確である。また、「民法典」がすでに非法人組織を自然人、法人と並ぶ第3の法的主体タイプとしていることを明らかにした場合、「他の組織」という概念は根拠がなくなり、「他の組織」を「非法人組織」に修正し、法的レベルで民事主体の区分を統一することを提案したい。
二、改正草案第4条第2項における「同時」の意味を明確にする
草案第4条第2項の規定を改正し、「行政再議機関が行政再議事項を処理する機構は行政再議機構である。行政再議機構は同時に行政再議機関の行政応訴事項を処理することを組織する」と規定した。同条の規定の中で、行政再議機構は行政再議機関の行政応訴事項を「同時に」処理し、ここでは「同時に」どのように理解すべきか。同時に双方の主体は誰か。「同時」がここで表現されているのは職責の重なりなのか、それともプログラムの共同進行なのか、「同時」はここで表現するのには曖昧な意味がある。そのため、改正草案はこの条が表現した法律の意味を明らかにし、より正確な言語を使用しなければならない。
三、行政再議案件における調停制度の運用を明確にする
草案第5条の規定を改正し、「行政再議機関は行政再議事件を処理し、調停を行うことができる。」「調停は合法、自発的な原則に従わなければならず、国益、社会公共利益と他人の合法的権益を損なってはならず、法律、法規の強制的な規定に違反してはならない」と規定した。
法的には、調停の本意は双方が譲歩することだ。調停のこの本質的な特徴は行政管理関係に合致せず、もちろんすべての行政再議にも合致せず、少なくとも主要な行政再議に合致しない。行政再議所が受理したのは行政機関と自然人、法人と非法人組織間の管理関係であり、このような法律関係の特徴は、管理と服従、行政機関が享受する社会管理権、権力であり、管理対象は服従する義務しかない。だから法に基づいた行政の基本的な要求は、行政管理機関の職権及び職権を行使する手続きを厳格に限定することである。管理対象者が行政再議を提起したのも、行政機関が行使した職権が法に根拠があるかどうか、および手続きに合致しているかどうかに対するものである。行政再議所が解決しなければならない問題もここにある。このポイントでは、どのように介入し、どのように行うかを調停するには、真剣に考える必要がある。調停は行政罰金の部分に適用でき、罰金の額で調停できることを理解する人もいる。この理解は適切ではないと思う。このやり方は、行政管理機関が法律で規定された素人に職権を行使させたり、法律に厳格に基づいて職権を行使したり、職責に背いたりすることができない問題を引き起こす可能性があるからだ。
民法上の調停は、民事主体は平等であり、民事権利は民事主体自身のものであるため、裁判所は当事者を譲歩させることができる。だから調停は、社会機関を通じて行うこともできる。しかし、行政管理関係の中で、行政機関をどのように譲歩させるかは、法的根拠がないと思う。また、調停は自発的な原則に従い、自発的とは当事者が心の中で真実に譲歩したいということを指す。しかし、行政管理関係の中で、管理者はどのように心から譲歩しているのだろうか。最も重要なのは、被管理者が行政機関の管理行為に自発的に服従しているかどうかであり、これは本質な問題ではない:被管理者が服従しても服従しなくても、行政管理行為の効果の発生に影響しない。
これらの分析に基づいて、私は、同改正草案中の調停原則、自発的原則などの規定は法理にも行政再議の本質にも合致しないと思う。この原則を削除することを勧めたい。
もし罰金額で交渉ができるのであれば、罰金額に関する部分にその点を明記すればよい。しかし、この草案は調停を原則としているが、これは明らかに間違っている。
四、行政再議作業員の法的職業資格を備える規定を整備する
改正草案第6条第2項は、「行政再議機関において初めて行政再議に従事する者は、国家統一法律職業資格試験を通じて法律職業資格を取得し、同一職前訓練を受けなければならない」と規定している。この条文の意味は積極的であり、行政再議工作員の専門化レベルを高め、行政再議工作の法治化を促すのに役立つ。しかし、この条文を第4条と結合して分析すると、改正草案第4条第1項、つまり「県級以上の各級人民政府及びその他の本法に基づいて行政再議の職責を履行する行政機関は行政再議機関である」という規定に基づいて、行政再議機関は原則として県級以上の人民政府であるという結論を出すことができる。
改正草案第4条第2項によると、行政再議機関が行政再議事項を取り扱う機関は行政再議機関であるが、行政再議機関は、政府に関わる全員を含んでいる。行政再議の決定を考慮して、行政再議機関の首長が署名することが多いルールでは、行政機関が再議に参加するこれらの首長は、国家の法律職業資格も必要ではないでしょうか。
実際、現在法的職業資格が求められているこれらの人は、再議機関のすべてのスタッフではなく、再議機関のスタッフだ。市長、県長は行政再議機関の職員で、法律職業試験に合格するように要求するのは現実的ではないと思う。
そのため、法律は行政再議機関と行政再議機関を2つの機関として区別し、誰が法律職業試験の資格を持つべきかを明確に規定しなければならない。そうでないと誤解が生じやすい。
五、民事主体が行政審議を提起する経路案内を完備する
改正草案の第2章および後の数章には、民事主体が行政再議を提起する経路、つまり誰に行政再議を提起するかという問題が規定されていない。これは明らかな欠陥である。自然人、法人、非法人組織は、行政行為に不満がある場合、行政再議を提起することができる。しかし、本法では民事主体が誰に再議を提起できるかは規定されていない。 民事訴訟の分野では、各区・県に1つの人民法院しかないため、訴訟を起こすのは地元のこの人民法院にある。したがって、裁判所の訴訟を規定する訴訟法は、その裁判所に提訴することを規定する必要はない。しかし、行政再議は異なる。改正草案第4条第1項によると、県級以上の各級人民政府及びその他の本法に基づいて行政再議の職責を履行する行政機関は行政再議機関である。しかし、県級以上の各級人民政府のほか、同じレベルの政府の中には、行政再議を管轄する権限を持つ機関が多い。例えば、本法第27条の規定に基づき、税関、金融、外貨管理などの垂直的な指導を実行する行政機関、税務、国家安全機関の行政行為は、上位の主管部門が受理する。この中に「等」の字があることに注意してください。また、どのような審議機関があるのか、法律にも規定されていない。
1つの再議機関に複数の再議機関があり、また現行の一部の法律では行政再議前置制度が規定されている[3]。これらの再議が前置されている場合、行政再議機関の下には専属行政再議管轄権を持つ機関があり、例えば国務院特許行政部門の下の特許再審委員会、そして国務院法制弁公室(現在は司法部、司法庁の再議機関と呼ばれている)に一括して渡された機関もある。だから、同じレベルの政府でも、今は複数の再議機関がある。
そのため、私はここで民事主体が行政再議を提起する経路案内を規定し、民衆がどのルートを通じて、先にどこに行って再議を提起するかを明確にするのに便利であることを提案したい。
六、行政再議事件の受案範囲を拡大する
改正草案11条は14項目の行政審議の対象範囲を規定しているが、行政審議は行政争議事件を解決する主要チャンネルであるため、対象範囲を拡大しなければならない。裁判所は1年に30万件の行政事件を受理しているが、行政審議事件は3万件に過ぎず、相対的に行政審議のメインチャンネルの役割が果たされておらず、受任範囲をさらに広げなければならない。
受訴範囲の拡大は、民事主体の権利義務に間接的に影響を及ぼす決定や行為を考慮しなければならない。例えば,道路交通事故責任認定は,交通事故の客観的事実を特定し,当事者の権利義務について直接決定を下していないが,このような決定によって生じた事実は間接的に当事者の権利義務に重大な影響を及ぼす可能性がある。このような決定は実際には多く存在するが,たとえば行政機関による議事録が当事者の権利義務を直接決定していない可能性もあるが、実際には当事者の権利義務に基礎的な制限を課し、間接的にその権利義務に影響を与えているケースもある.
したがって、行政審議法は、行政機関が民衆に直接的な処理をする事案や行政機関が民衆の権利に直接的な影響を及ぼす事案だけを対象にしてはならず、行政機関が民衆の権利を基礎的に制限し、結局間接的に民衆の権利に影響を及ぼす行政行為も対象としなければならない。
七、行政審議案件における第三者制度の明確化
改正草案第15条は、この法律で初めて「第三者」という概念を扱っている。改正草案第16条第1項の規定によると、申請者以外の行政行為又は事件処理結果と利害関係がある公民、法人その他の組織は、第三者として行政審議に参加することを申請することができ、又は行政審議機関から行政審議に参加することを通知される。しかし、本改正案は第三者のこの用語だけを規定しており、行政審議過程における第三者の規則を散発的に規定している。行政審議の過程で誰が第三者なのか、当事者がどのように行政審議に参加するのかという最も重要な立法規則もない。
この法律の多くの条文が第三者に規定されていることを考慮して、私は本法第一章で行政審議申請人を規定した後、どのような人が第三者に属するのか、彼らがどのように行政審議手続きに入るのかについて明確な規定を制定しなければならないと建議したい。その後、第二章で行政審議開始段階で第三者申請の受理過程について詳しく規定しなければならない。
八、行政審議手続の空転を回避
改正草案63―65条は、行政審議機関が行政行為を撤回したり、違法行為を確認できるように規定しているが、行政行為を撤回したり、違法行為を確認した後、どの機関が行政行為を変更しなければならないのか、どのように変更しなければならないのかについては行政審議法に規定されていない。実生活では審議機構が審理後に行政行為を元の行政機関に送り返し、元の行政機関が行政行為をやり直す場合が多く、このような場合には手続きが空転し、国家行政資源や申請者の時間的コストを浪費するという問題が生じる。中央政法委、最高人民裁判所の張軍院長がこの問題を提起したことがあるが、手続きの空転は事件処理の質的効率を高め、実体的公正と手続き的公正な統一に不利だ。[4]
改正草案のこの3つの項目から分かるように、いくつかの行政審議は審議機構が自ら行う行為であり、司法部(すなわち国務院法制処システム)が本来主管していた行政審議行為ではないことを発見した。したがって,当施設が行った行為であれば,本人は当施設が直接行政行為を行うべきであることを提案すればよいと考えられ、元の行政行為作成機関に再送する必要はないと考えている。事件を単刀直入に解決し、民衆の問題を解決して手続きが空転しないようにすることができる。
九、第65条の作文規範を完備する
改正草案第65条は次のように規定している。
「行政行為は、行政審議機関が当該行政行為を撤回しないものの、当該行政行為が違法であることを確認する場合のいずれかに該当する。
(一)行政行為は法律に基づいて撤回すべきであるが、撤回は国益、社会公益に重大な損害を与える。
(二)行政行為の手続は軽微で違法であるが、申請者の権利に実質的な影響を及ぼさない。
行政行為は次のいずれかの場合があり、撤回又は履行を命ずる必要がない場合、行政審議機関は当該行政行為が違法であることを確認する。
(一)行政行為は違法であるが、撤回可能な内容を有しないこと。
(二)被申請者が元の違法行政行為を変更しても、申請者は元の行政行為が違法であることを撤回又は確認することを要求する。
(三) 被申請者が法定職責を履行せず、又は遅延させた場合、命令の履行は意味がない。"
本条の規定は二つの項目を規定しているが、この二つの項目間の記号表現についてはやや混乱して規範的な法律規定様式に合致しない。例えば、上条第1項の後に括弧で表現される2つの項目が規定されているが、後に続く3つの項目も括弧で表現される。専門的に法律を勉強するのではなく、専門的な研究がない人たちには混乱が生じやすい。
したがって、法の明確化という観点から、第65条に対して次のようないくつかの提案がある。
一つは65条を二つの条文に分けなければならないということだ。現在、第65条には二つの規定があるが、第1項は二つの号、第2項は三つ号であり、素人の理解に不便だ。両項目の関連性を綿密に分析した結果、行政行為の違法性を確認することは経済的でないものと不可能なものの二つだった。しかし、法条文がはっきりしているという点で二つの条文にしなければならない。
第二に、行政行為の違法性を確認する結果が不明確だ。両条項とも行政行為の違法性を確認したが、撤回しないとしたが、撤回しない場合の法的結果は明確ではない。第1項2号は、申請者の権利に実質的な影響を及ぼさないが、第三者に影響を及ぼす可能性はないか。影響がある場合は,他の条文に誘導して処理する必要がある。行政行為の違法性の確認だけで、実質的な結果がない。
以上の提案は、ご参考までに。